報告書 2007年3月8日 中岡哲郎セミナー 於 神戸大学国際文化学部
E.H. Hunterの生涯
神戸大学国際文化学部 塚原研究室
小原昂大
■
はじめに
本報告書は、2007年3月8日、神戸大学に中岡哲郎先生をお招きしておこなったセミナーでの発表の概容をまとめたものである。
神戸・三宮の中心街から北野・異人館へと抜ける南北の道の一つに「ハンター坂」と呼ばれる坂道がある。これは、明治時代において神戸を中心に活躍したイギリス商人、E.H.ハンターの自宅と商人をつなぐ道であったことに由来する。自宅と職場を結ぶ道、というのは働く人になら誰しもにあるものだが、そこに自分の名がつく、ということを想起してみればその人物の影響力・知名度の大きさがいかほどであったかがわかるだろう。
旧ハンター邸は現在、神戸王子公園内に移築されているが、私はそのハンター邸が当時位置した現在の北野異人館周辺を訪ねてみた。いつもは北野坂を上がるところを、せっかくだから、と道をいくつか西にずらして「ハンター坂」をのぼってゆく。道中は現在も多くの商店やレストランでにぎわっていた。ほどなく、旧ハンター邸の正門跡に辿り着く。すると、そこから5分ほど歩いた場所に鉄で“H”と刻まれた塀があることがわかる。もちろん、Hunterの頭文字のHである。私の早足で5分かかる距離を、一手に有していたハンターという人物。一体どんな人だったのだろうかと、期待と想像は膨らんだ。
■ハンターの略歴
さて、ここでハンターについて基本的な情報を見ておくべきだろう。
まず、ハンターは1868年に来神し、さまざまな事業を手がけ、日本の近代化に尽くした人物として知られている。また、日本人の妻(平野愛子)を娶り、子どもたちにも日本籍を取得させるなど親日家であったとして評判の高い人物でもある。これらは多くの書籍に共通して見られる氏についての評価であるし、1909年、当時の外国人としては異例の勲五等双光旭日賞を明治天皇から賜っていることもその評判の高さを裏付けるものである。
次に、氏がそれほどまでの富と名声を得るに至るまでの略歴を見よう。次ページのスライドにまとめてあるが、オーストラリア・香港・上海という日本に至るまでの経路は、神戸造船所にて氏の上司となったE.C.キルビーのそれとほぼ同様であり、当時ゴールドラッシュに沸いた豪州など、さまざまなビジネスチャンスを求めた結果、日本に辿り着いたものだと推測される。
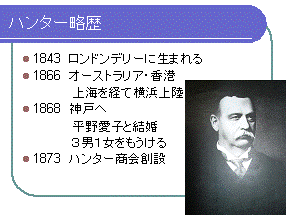
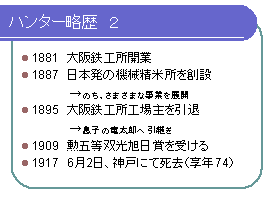
E.C.キルビーの下、神戸造船所で働いた後、同僚であった秋月清十郎とともに独立し、ハンター商会を創設。当初は経営不振にあえぐものの、1877年の西南戦争における特需での利益により経営基盤を固めることに成功したハンターは1881年、大阪鉄工所を開業する。この大阪鉄工所は氏の生涯最大の事業だったと言え、また現在の日立造船株式会社の前身であることも記しておかなければなるまい。
ハンターと日立造船の現在の関係についていうと、『日立造船七十五年史』には表紙を開いてすぐに氏の肖像が見られたり、氏の墓標のすぐ脇に立派な顕彰碑が日立造船によって建てられていたりと、その事業を起こしたハンターに対しての敬意と謝意は十分に読み取れる。また、氏は現在、神戸・再度山の外国人墓地に眠っている。氏の墓は私の背の倍はゆうにある立派なものであり、妻の愛子氏が“Ai Hunter”として共葬されていることや、フリーメイソンのマークが刻まれていることもわかった。同じ墓地の中でも群を抜いて大きな墓標であり、ハンターがいわゆる成功者であったことを改めて思い知ることとなった。
■大阪鉄工所
ハンターは実に幅広く、さまざまな事業を手がけているが、今回の報告ではその中でも最大の事業であった「大阪鉄工所」を中心に取り上げた。以下、私が特に気にかかった事柄をピックアップした略年表である。発表に関わるものを中心にとりあげたので、やや恣意的なものになっている、ということはお断りしておきたい。
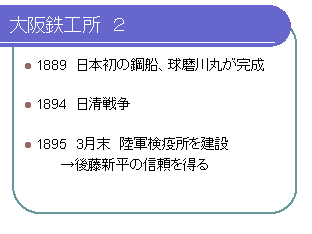
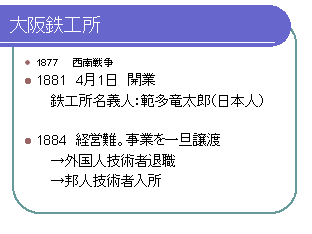
大阪鉄工所は1881年に開業されたが、その当初から鉄工所の名義人はハンターの息子である竜太郎とされた。「竜太郎」という名からもわかるようにハンターは息子に日本籍を取得させ、「範多家」を開かせた。これは、当時、外国人経営の工場の立場が弱かったこと、加えて、かつての上司であるキルビーによる神戸造船所の顛末を見てきた経験を踏まえてのことであったと考えられる。とは言っても当時、息子はまだ10歳少々である。とても鉄工所を経営できるとは思えない年齢であるが、名義人を日本人にすることにこだわりつづけたことにハンターの貪欲に生き残ろうとする姿勢が垣間見える。
その後、鉄工所の経営難を精米所や煙草会社、煉瓦会社などに触手を伸ばすことでなんとか切り抜けながら、日本発の鋼船「球磨川丸」を完成させるなど、事業は次第に成功をおさめてゆく。
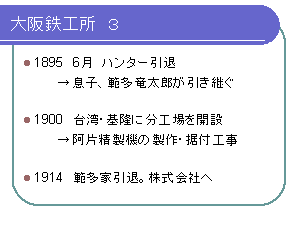 1894年からの日清戦争が終結し、大阪鉄工所に陸軍検疫所の建設が依頼される。依頼主は相馬事件による衛星局長罷免からの回復を図る後藤新平であった。検疫所の規模に比して期限は法外に短かったが、大阪鉄工所はわずか数日の遅れを出したのみで完成させ、後藤の信頼を得ることになる。
1894年からの日清戦争が終結し、大阪鉄工所に陸軍検疫所の建設が依頼される。依頼主は相馬事件による衛星局長罷免からの回復を図る後藤新平であった。検疫所の規模に比して期限は法外に短かったが、大阪鉄工所はわずか数日の遅れを出したのみで完成させ、後藤の信頼を得ることになる。
その後、台湾総督府民政長官となった後藤は経済改革とインフラ整備を進めてゆくが、その事業の一環として基隆の港湾整備と、当時の台湾で蔓延していた阿片の規制に取り組んだ。しかし、阿片の輸入自体が厳しく制限されていた日本では阿片は流行することもなく、従って阿片に対する知識やその専門家がほぼ皆無であった。
後藤はかつて衛星局長であった経験も踏まえ、阿片規制に力を注ぐが、突然全面禁止にすることによる民衆の蜂起を防ぐため漸禁策をとった。その概容は、阿片を日本政府の専売制とすることで入手を困難にし、加工してから流通させることで当時最も問題視されていた生阿片の吸飲・給食を防ごうとするものであった。しかし先述の通り当時の日本には阿片に対する知識がなかった。そこで、白羽の矢が立ったのが大阪鉄工所である。
以前の陸軍検疫所の建設において後藤の信頼を得ていたことに加え、大阪鉄工所は既に日本でも有数の技術を誇っていた。また、イギリスという「帝国」につながりを持つ、ということも少なからず考慮に入ったと推測できる。後藤は「英領インド並」の設備を目指したそうであるが、その期待を一身に背負い、大阪鉄工所は台湾・基隆に分向上を開設する。
ここで考えたいのは、宗主国と植民地間における技術移転についてである。私はその技術移転に次の2通りがあると考える。
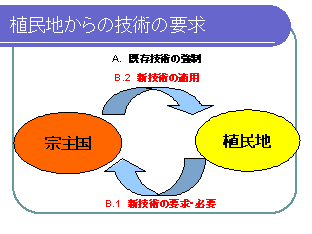 一つは、インフラの整備や鉄道の敷設など、宗主国に既存の技術を植民地に強制するかたちで行われるものである。
一つは、インフラの整備や鉄道の敷設など、宗主国に既存の技術を植民地に強制するかたちで行われるものである。
もう一つは、宗主国には存在しなかった技術が植民地を統治することになって初めて必要とされ、そこで生まれた新しい技術が植民地へと折り返して適用されるというものである。この場合、宗主国は自国内で新技術を開発することもあれば、どこか他国から技術を輸入するということもあろう。しかし、いずれにせよ重要なことは、この場合、植民地だけでなく、宗主国側にも新たな技術が生まれ、育まれるということである。
これまで概観した大阪鉄工所による阿片精製機事業は二番目のケースに含まれるだろう。植民地が植民地にならないでいれば、つまり台湾が日本の統治下に入らなければ台湾内で阿片規制を行うための技術発展は起こらなかったかもしれないし、少なくとも時期がもっと遅れたことは疑いない。しかし、日本にとっても台湾を統治することにならなければ阿片に対する技術、ひいては知識も育まれることはなかっただろう。理由は至極単純だ。必要のないことだからである。台湾を統治することになって初めて新しい技術に対する必要が生じた。つまり、宗主国と植民地との出会いは宗主国側にも技術の発展をもたらすのだ。
誤解のないように付け加えると、双方に技術発展をもたらす植民地制度というものは素晴らしい、と言っているのではもちろんない。しかし、植民地への既存技術の強制ばかりが強調されすぎるのは事実を見えにくくしてしまう。
■まとめとして
大阪鉄工所の台湾阿片精製機事業について多くを書いたが、ハンターに話を引き戻そう。
すなわち、政府の勅命とあればハンターは阿片に関わる事業も、海外への進出も躊躇しなかった。幅広くさまざまな事業を手がけたことの一環としても見ることはできるし、政府に取り入ってあわよくば戦艦の注文をも取り付けようとしたという見方もできるだろう。いずれにせよ、ビジネスチャンスを逃すまい、とアンテナを張り巡らせていた根っからの商人であったことは間違いがないようである。
とすれば、日本への技術的貢献も、自分が企業家として生き残ろうとした結果の副産物であるという辛い見方もできる。さらには日本人妻を娶り、子どもたちに日本籍を取得させたことも戦略的なことであって、「親日家」という評価にも疑問は残る。いくらでも辛い見方はできるし、推測の域を出ないではあるが、研究を続けてゆく価値はありそうだ。